欧州から、ウェブの勢力図を塗り替えかねない、とんでもないニュースが飛び込んできました。巨大プラットフォーマーであるGoogleが、その中核サービスであるAI検索機能を巡って、独立系の出版社グループから欧州連合(EU)の独占禁止法に違反するとして申し立てを受けたのです。
「また大手企業同士の揉め事か」と感じるかもしれません。でも、これは決して他人事ではないんです。この一件は、AIが私たちの作ったコンテンツをどう扱うか、そしてその対価は支払われるべきなのか、という根源的な問いを突きつけています。デザイナーとして、そして一人のクリエイターとして、このニュースの持つ意味は計り知れないと感じています。
これは、AI時代のクリエイターエコノミーの未来を占う、極めて重要な「事件」。今回はこの申し立ての核心に迫り、様々な角度からその影響を読み解き、私たちクリエイターがこれからどう動くべきかの道しるべを探っていきます。
この記事で分かること📖
⚖️ 事件の核心: なぜ出版社たちはGoogleを訴えたのか、その具体的な理由を3つのポイントで解説。
🏢 両者の戦略: Googleと出版社、双方の主張と、その裏にある巧妙な戦略や駆け引きを読み解く。
🤔 クリエイターへの影響: この問題が私たちデザイナーやライターにどう関係するのか、AI要約機能の価値とリスクを多角的に深掘り。
🧭 未来への道しるべ: クリエイターが今から取るべき「守り」と「攻め」の具体的なアクションを提案。
一体何が起きた?事件の概要をわかりやすく解説
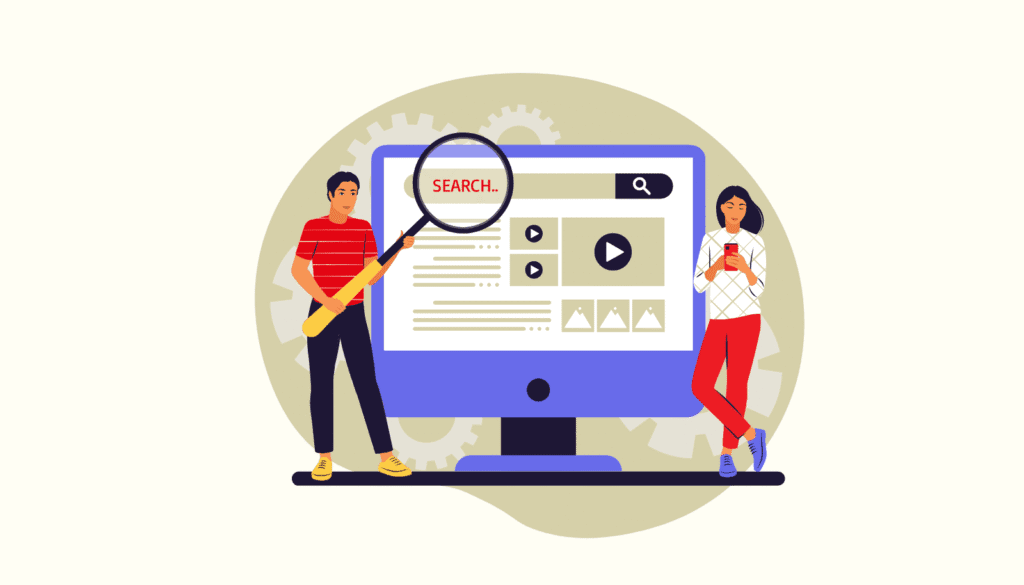
まずは、この「事件」の全体像を冷静に掴んでおきましょう。一体誰が、誰を、なぜ訴え、何を求めているのでしょうか。
- 申し立てたのは誰?
非営利連合体である「独立出版社同盟(Independent Publishers Alliance)」をはじめとする、欧州各国の独立系メディアのグループです。ニューヨーク・タイムズのような巨大メディアではなく、規模は小さくともウェブの多様性を支えてきた、いわば現場のプレイヤーたちが声を上げました。 - 相手は誰?
言わずと知れた、米アルファベット(Alphabet Inc.)傘下のGoogle。同社は、検索エンジンで世界を席巻したのを皮切りに、動画プラットフォームのYouTube、スマートフォンのOSであるAndroidなど、私たちのデジタルライフに不可欠なサービスを次々と展開してきた巨大IT企業です。近年は「AIファースト」を経営の中心に据え、既存の全事業をAIで再定義しようと莫大な投資を行っており、今回のAI要約機能はその象徴的なサービスと言えます。 - 問題となっているのは?
Googleが検索結果の最上部に表示するAIの要約機能「AI Overviews」(かつてSGEの名で知られた機能の正式版です)。この機能の心臓部には、Googleの最先端大規模言語モデル(LLM)「Gemini」が搭載されており、ユーザーの質問に対して、ウェブ上の複数の情報源を統合・要約し、一つの包括的な回答を生成します。
この回答生成は、①ユーザーの質問受信 → ②ウェブから関連情報を検索 → ③収集した情報でAIを補強(グラウンディング) → ④AIが最終的な回答と出典を生成、というプロセスで行われます。
最大の変化は、このAI要約機能が検索結果ページの「ポジション・ゼロ」と呼ばれる最上部を占有し、デスクトップでは画面の最大42%、モバイルでは48%もの領域を占めることがある点です。これにより、従来のオーガニック検索結果は物理的に下方へ追いやられ、ユーザーの視覚的な階層構造が根本から覆されることになります。
この機能が、EUの独占禁止法(EU機能条約第102条)が禁じる「市場での支配的地位の濫用」にあたると、出版社側は主張しています。 - なぜ問題なの?
出版社側の主張はシンプルかつ深刻です。AI Overviewsが答えを要約してしまうことで、ユーザーが自分たちのウェブサイト(オリジナルコンテンツ)を訪れなくなり、トラフィック(アクセス数)と、それに伴う広告収入が激減する。これは事業の存続を脅かす「回復不可能な損害」だと訴えています。 - 何を求めている?
彼らが求めているのは、単なる謝罪や賠償金ではありません。損害が手遅れになる前に、AI Overviewsの運用を一時的に停止させるための緊急措置、「暫定措置」です。これは、彼らが置かれている状況がいかに切迫しているか、数年にわたる法廷闘争を戦い抜く体力すらないと考えていることの表れです。
注目ポイント📌
🚨 独立系出版社がGoogleを「独占禁止法違反」で申し立て。これはウェブのルールをめぐる重要な戦い。
🆘 彼らが求めるのはAI要約機能の停止という「暫定措置」。それほど事態は切迫している。
📜 舞台はEU。過去にGoogleへ巨額の制裁金を科した、プラットフォーマー規制の最前線。
出版社たちの悲痛な叫び – 奪われる3つの価値

なぜ彼らは、巨大なGoogleを相手に、ここまで踏み込んだ行動に出たのでしょうか。
その背景には、AI要約機能によって奪われつつある、3つの決定的な「価値」に対する危機感があります。これは、Googleが自らのエコシステムの基盤であるコンテンツ提供者を侵食する「自食作用(カニバリゼーション)」とも言える現象です。
トラフィックという「生命線」
サイトにとって、訪れる人の数(トラフィック)は、人間でいう血液のようなものです。しかし、このAI要約機能は、検索結果の画面上で直接答えを教えてしまうため、ユーザーがわざわざ記事のリンクをクリックする必要がなくなります。いわゆる「ゼロクリック検索」が増えてしまうのです。
この影響は、具体的な数字にも表れています。調査によると、AIの要約が表示されると、記事がクリックされる割合は平均15.5%〜35%も下がり、サイトによってはGoogle検索から訪れる人が20%〜60%も減ってしまったという報告もあります。
この状況に、多くのサイト運営者は「Googleとの約束が破られた」と感じています。
これまでは、「私たちが良い記事を作れば、Googleがお客さんを送ってくれる」という、一種の持ちつ持たれつの関係が成り立っていました。しかし今、その関係は一方的に壊され、Googleだけが得をする「搾取」に変わりつつある、と彼らは訴えているのです。
コンテンツという「資産」
記事や写真、イラストといったコンテンツは、クリエイターや出版社が時間、労力、そしてコストをかけて生み出した大切な「資産」です。今回の申し立てでは、Googleがこの資産を二重に、しかも無断で利用していると非難しています。
- 要約のための利用: AI Overviewsの要約を生成するために、コンテンツが利用される。
- AI学習のための利用: その裏で動く大規模言語モデル(Gemini)を賢くするために、コンテンツが学習データとして利用される。
これは、汗水流して育てた農作物を、ある日突然、断りもなく収穫され、しかもその農作物を使ってライバルが商売を始めているようなものです。この「コンテンツのタダ乗り」とも言える構造に、彼らは我慢の限界を迎えたのです。
選択という「自由」
「AIに使われたくないなら、設定で拒否すればいいだけでは?」と思うかもしれません。しかし、ここにGoogleの巧妙な、そしてサイト運営者から見れば「横暴」とも言える仕組みがあります。
現状、AIの要約機能に記事が使われるのを拒否しようとすると、なんと、あなたのサイトはGoogle検索の結果に表示されなくなってしまいます。
これは、ウェブで活動する者にとって、「AIに記事を使わせるか、インターネット上から存在を消すか」という、あまりにも過酷な選択です。生き残るためには、事実上、参加を強制されているのと同じ。これこそが、彼らが「巨大な力を利用した不公平なやり方だ」と訴える一番の理由なのです。
さらに言えば、Googleは、AIが得意とするような「より複雑な質問」をユーザーがするように、巧みに仕向けている節があります。こうして、AIの価値をどんどん高め、ユーザーをGoogleのサービスから離れられなくすることで、ウェブの世界全体のルールを自分たちに都合よく書き換えようとしている、と見られています。
注目ポイント📌
🩸 AI要約機能はサイトへの血流である「トラフィック」を止め、ビジネスモデルを破壊する。
🖼️ クリエイターの大切な「資産」であるコンテンツが、同意も対価もなく利用されている。
😠 Googleが突きつけるのは「参加か、死か」という理不尽な選択。クリエイターに「自由」はない。
Google側の言い分と巧妙な戦略
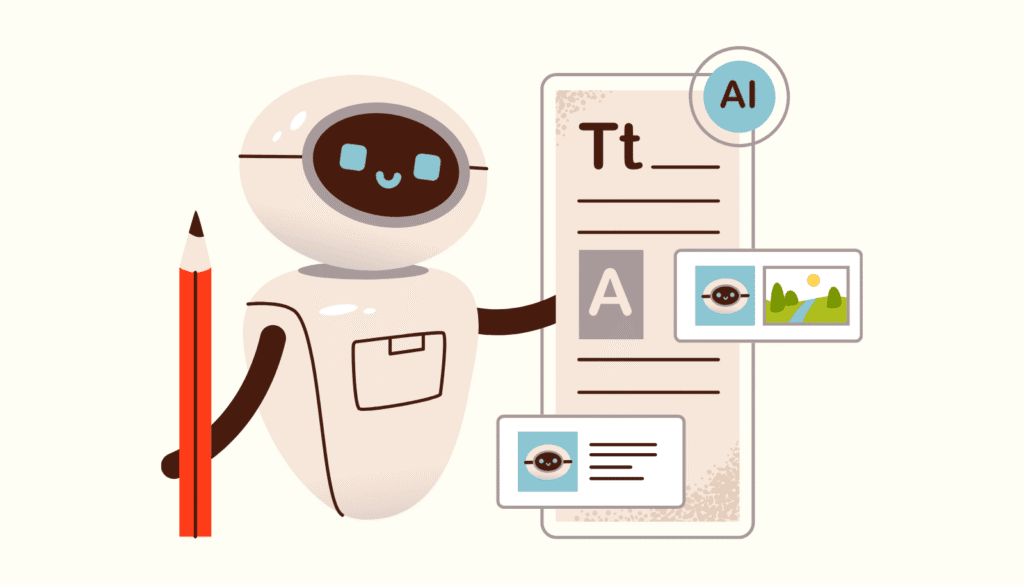
もちろん、この申し立てに対してGoogleも黙ってはいません。物事を多角的に捉えるため、彼らの主張にも一度、落ち着いて耳を傾けてみましょう。
Googleの防御戦略は、出版社側の具体的な指摘(トラフィック減少や強圧的な選択肢など)に正面から向き合うのを避け、より大きな視点へと議論をずらす、非常に計算されたものです。
彼らが主に主張するのは、以下の2点です。
- 「AI要約機能は新しい発見の機会を創出する」
Googleは、AI体験が、ユーザーにこれまで以上に複雑な質問を投げかけることを可能にし、それが結果として「ウェブサイトやビジネスが発見される新たな機会を生み出す」と主張します。つまり、目先のクリックは減るかもしれないが、より質の高い、関心の強いユーザーを送客できるというわけです。 - 「我々はウェブに多大な貢献をしている」
「毎日、何十億ものクリックをウェブサイトに送っている」というマクロな事実を強調します。個々の出版社の損害というミクロな話を、ウェブ全体への貢献という大きな話に持ち込むことで、問題を矮小化しようとする狙いが見て取れます。
巧みな技術的防衛線「Google-Extended」
さらにGoogleは、「AIにコンテンツを使われたくないなら、ちゃんと対策がありますよ」と主張しています。それが「Google-Extended」という、サイト側で設定できる一種の”お断り”の意思表示です。
しかし、ここには非常に巧妙な線引きがあります。この設定でブロックできるのは、AIを「賢くするための教科書」として、あなたの記事が使われること(AIの学習)だけなのです。
AIが「検索結果の要約を作る」ためにあなたの記事を読むことは、残念ながらブロックできません。
Googleは、前者を「AIの学習」、後者を「検索サービスの一部」と、全くの別物として扱っているからです。
このやり方はとても巧妙です。Googleは「AIに学習されたくない人のために、ちゃんと拒否する方法を用意しています」とアピールできます。その一方で、「AIの要約は、昔からある検索結果の紹介文が少し進化しただけです」と言って、記事の利用を正当化できるのです。
このような駆け引きは、AIという新しい技術が社会に広まっていく中での、避けられない「産みの苦しみ」なのかもしれません。
注目ポイント📌
🎁 Googleは「AI要約機能は新たなチャンス」と主張し、個別の損害から目を逸らさせようとしている。
🤔 議論を「ミクロな損害」から「マクロな貢献」へとすり替える、巧みな広報戦略。
⚙️ AIの「学習」は拒否できても「検索での利用」は拒否できない。巧妙に設計された技術的な壁。
これは他人事じゃない!私たちクリエイターへの影響とAI要約機能の価値
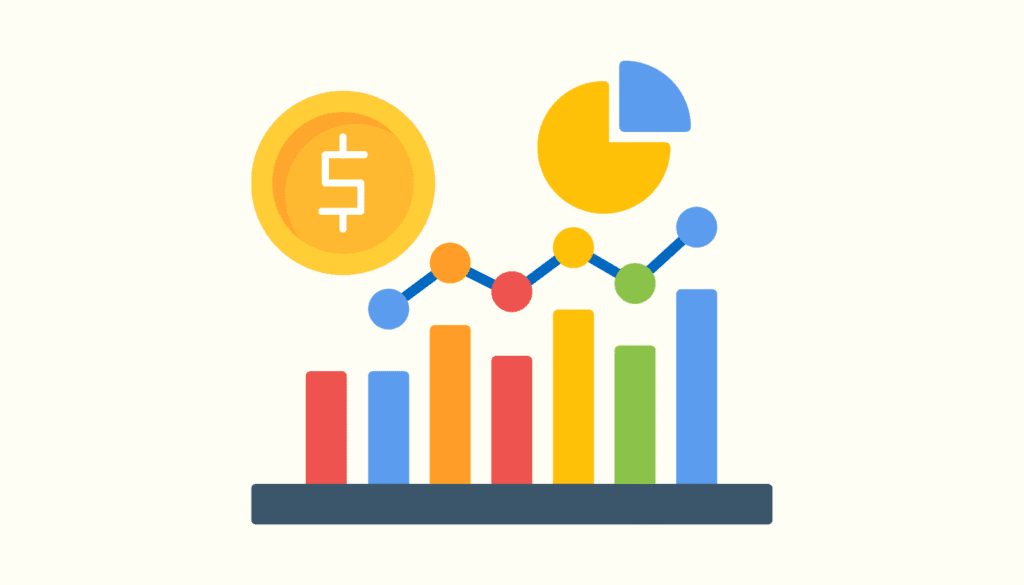
さて、ここからが本題です。この欧州での法廷闘争は、遠い国の話ではありません。ウェブ上でコンテンツを発信する私たち全てのクリエイターに、直接的・間接的に大きな影響を及ぼします。
しかし、話は「トラフィックが奪われる」という単純な脅威だけでは終わりません。このAI要約機能は、トラフィックを破壊する「共食いする者(カニバル)」であると同時に、トラフィックを再分配する高度な「キュレーター」としての一面も持っているのです。
衝撃の事実:「引用プレミアム」という逆転現象
「AIのせいでサイトに来る人が減ってしまう」――多くの人がそう心配していますよね。
しかし、実際のデータは、その逆とも言える驚きの事実を示しています。なんと、AIの要約文に「この記事を参考にしました」と紹介(引用)されると、アクセスが減るどころか、むしろ大幅に増える可能性があるのです。
この現象は、AIからのお墨付きとも言える「引用プレミアム」と呼ばれています。調査によると、AIに引用されたページは、されなかったページよりも、はるかに多くクリックされていることが分かっています。
| キーワードの種類 | AI要約機能が表示された場合の影響(クリック率の変化) | 解説(なぜそうなるのか?) | |
|---|---|---|---|
| ブランドキーワード (例:「〇〇社 製品名」など) | 平均 +18.7% 増加 | ユーザーの目的が明確で、AIの要約が「最後の後押し」や「答え合わせ」として機能するため。AIからのお墨付き(引用プレミアム)で、さらに信頼性が高まる。 | |
| 非ブランドキーワード (例:「〇〇 おすすめ」など) | 平均 -20.0% 減少 | AIが直接答えを見せてしまうため、ユーザーがサイトを訪れる必要がなくなる。最も「共食い」の影響を受けやすい。 | |
出典: 主にAmsive社の調査データを基に、Wordstream社、SE Ranking社のレポートの文脈を加えて作成
かつては、何をおいても検索結果の1位を目指すのが当たり前でした。しかし今では、たとえ検索順位が8位のページでも、AIがその内容を「素晴らしい」と判断して引用すれば、1位のサイトよりも多くの人が訪れる、という「下剋上」が起こり得るのです。
- Google AI Overviews: New CTR Study Reveals How to Navigate Click Drop‑Off:Amsive社が700,000のキーワード、5業界、10ウェブサイトを対象に調査した結果、Googleの AI Overviews(AIO) が表示される検索でのCTR(クリック率)が平均 15.49%減少していることを明らかにした記事
- 34 AI Overviews Stats & Facts [2025] – WordStream:WordStreamの記事(2025年6月25日更新)は、Googleの「AI Overviews」(AIO)に関する最新の統計・傾向を34項目にわたって紹介しています。
- The Google SGE Snippet Study:SE Ranking が実施した大規模調査で、2024年~2025年における Google の SGE スニペット(AIによる要約表示)の出現頻度や構成要素、SEOへの影響などを包括的に報告しています
では、何が引用されるのか?品質フィルター「E-E-A-T」の重要性
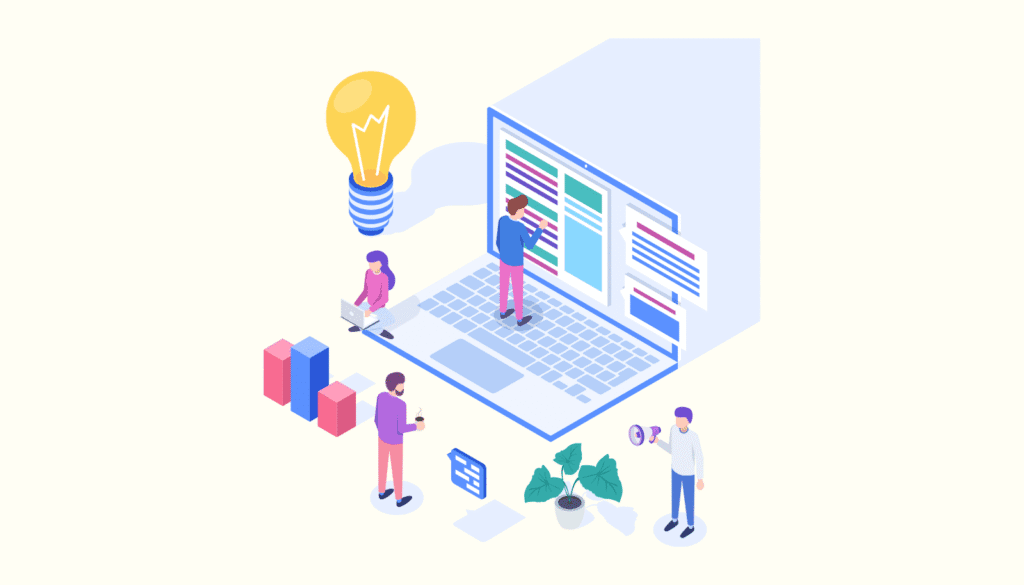
では、AIは何を基準に引用元を選んでいるのでしょうか。その答えこそ、Googleが長年ウェブサイトの品質評価の根幹に据えてきた「E-E-A-T」という概念です。
- Experience (経験): AIには生成不可能な、書き手の一次的な実体験に基づくコンテンツ(商品レビュー、ケーススタディなど)。
- Expertise (専門性): トピックを深く掘り下げた包括的なコンテンツ、信頼できる外部情報源への引用。
- Authoritativeness (権威性): サイト全体の評判、特定トピックへの集中度、質の高い被リンク。
- Trustworthiness (信頼性): 情報の正確性、透明性(著者情報など)、サイトの安全性。
「要約されるコンテンツ」と「引用されるコンテンツ」
この品質フィルターは、コンテンツを二種類に峻別します。
- 脆弱なコンテンツ: 単純な事実や定義に関する記事は、AIに要約され、クリックを失いやすいです。
- 引用されやすいコンテンツ: 一方で、独自のデータや分析、AIには生成できない人間の経験や専門家の意見が豊富なコンテンツは、引用の対象となりやすいです。
さらに、AIは複雑な質問を受けると、それをいくつかの簡単な質問に分解して、それぞれ個別に答えを探しにいきます。
この賢い仕組みのおかげで、たとえ有名なサイトでなくても、ある特定のニッチな問いに完璧に答えているページがあれば、AIがそれを見つけ出し、紹介してくれるチャンスが生まれるのです。
クリエイターにとってのAI要約機能の価値とは?
このキュレーターとしての一面は、私たちクリエイターにとっても大きな価値を持ちます。
- リサーチの超高速化: 複雑なテーマの要点を瞬時に把握し、より本質的な「考える」時間に集中できます。
- アイデアの壁打ち相手: インスピレーションの源となるアイデアやキーワードを提示してくれます。
- 技術的な問題の解決: コーディングやソフトウェアの使い方のヒントを直接得られます。
つまりAI要約機能は、私たちの単純作業や情報収集の時間を肩代わりし、よりクリエイティブな活動に専念させてくれる可能性を秘めたツールでもあるのです。
注意事項⚠️
🤔 AI要約機能はトラフィックを奪う「脅威」であると同時に、質の高いサイトへ送客する「キュレーター」でもある。
💎 従来の順位より「引用される価値」が重要に。その鍵はE-E-A-T、特に一次情報や専門性。
💡 ニッチな専門性を持つサイトにも、クエリ・ファンアウト技術により光が当たるチャンスがある。
AI要約が当たり前に。私たちはどこへ向かうべきか?
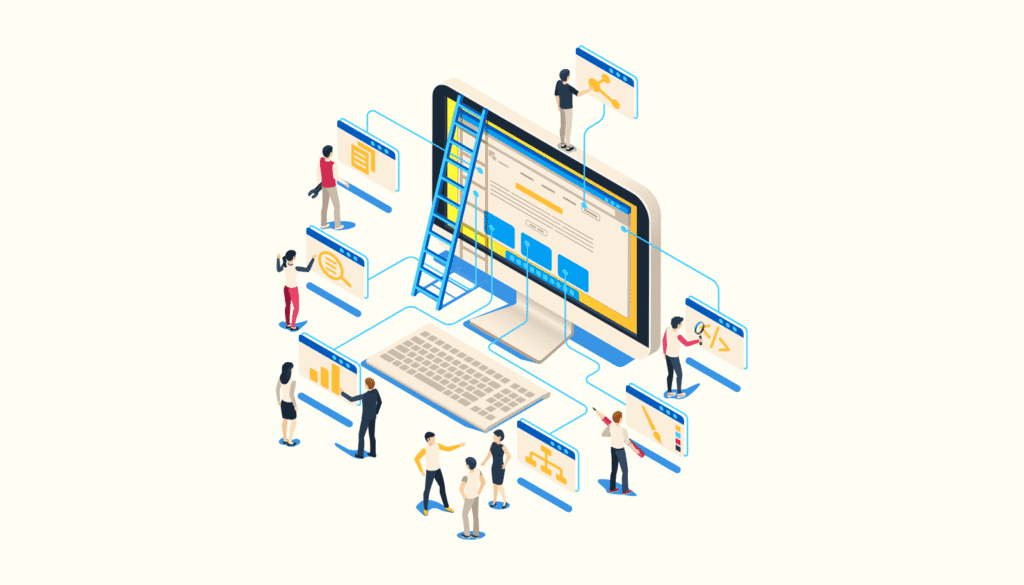
この新たな現実に対応し、むしろそれを活用して成長するための、具体的かつ実行可能な戦略が求められます。
守りの戦略:AIに「引用させる」コンテンツ作り(AEO)
AI Overviewsのような要約機能が一般化し、ChatGPTやPerplexityのような高性能な生成AIが普及する中で、浅い情報をただ並べただけの記事は、今後ますます価値を失っていくでしょう。
にもかかわらず、速報性や転載中心のメディアが依然としてSEOで強い現状は、Googleが掲げる「質の高い情報を評価する」という方針と矛盾しているようにも見えます。もちろん、ドメインの信頼性や被リンクの蓄積といった技術的な要因が関与しているのは理解できますが、それが結果として「内容が薄い大手メディア」が上位に表示され続ける要因となっているのも事実です。
しかし、AIの進化スピードを考えれば、情報精度は今後さらに高まり、「情報が早いだけで内容が浅いコンテンツ」の価値は急速に低下していくでしょう。
一方で、一次情報や深い考察、専門性に裏打ちされたコンテンツの価値はむしろ高まるはずです。
AIの進化は、私たちに「本質」で勝負することを求めています。「長年やっているから強い」という時代は終わりを告げ、「本当に価値のある情報を出しているか」で勝負する時代が、いよいよ本格的に到来しているのです。
これからの戦略は「AEO(AIエンジン最適化)」です。
AEOフレームワーク:引用されるための最適化
- アンサー・ファースト: 記事の冒頭で、中心的な問いに簡潔かつ直接的に答える。
- 明確なフォーマット: 見出し階層(H2, H3)、箇条書き、表などを活用し、情報を論理的に構造化する。
- スキーママークアップの実装: FAQスキーマや著者スキーマなどの構造化データで、ページ内容をAIに正確に伝える。
- E-E-A-Tの明示: 権威ある著者情報の明記、信頼できる情報源への引用、独自データや経験の提示を徹底する。
攻めの戦略:依存からの脱却と「自分の庭」の創造
AEOは戦術ですが、長期的な成功のためには、より根本的な戦略転換が求められます。それは「脱・Google依存」です。
アグリゲーター(配信メディア)の黄昏
GoogleのAIは賢く、同じ記事が複数のサイトにある場合、どれが「大元」の記事なのかを見分ける力を持っています。
そのため、Yahoo!ニュースのように他社から記事を集めて表示するサイト(情報収集サイト)は、AIが紹介する記事の出典として選ばれにくくなります。結果として、本来Yahoo!ニュースに行くはずだった読者が、直接、大元の記事サイトに送られてしまう「中抜き」が起こりやすくなるのです。
この動きは、Googleが「有名サイトが、その評判を利用して中身の薄い他人の記事を載せること」を取り締まっている流れとも一致しており、「価値があるのは、記事を配ることではなく、最初に創り出すこと」というGoogleの強いメッセージが表れています。
LINEヤフーが独自のAI開発に巨額の資金を投じているのも、Googleの土俵で戦うのをやめ、自社がルールを決められる「囲い込まれた独自のサービス(庭)」を築くことで、この構造から抜け出そうとしているからなのです。
デスティネーションメディアへの転換
私たち個人クリエイターも、この流れから学ぶべきことがあります。
それは、検索で有利になるキーワードだけを狙って記事を大量生産するやり方から卒業し、読者が「このサイトの情報が読みたい」と、わざわざ目指して訪れてくれるような、信頼される「目的地」のようなサイトになることです。
- ダイレクトな関係構築: ニュースレターやLINE公式アカウントで、読者の連絡先という「資産」を築く。
- コミュニティの形成: DiscordやSlack、PatreonやFanboxなどで、熱量の高いファンと繋がる「居場所」を作る。
- 技術的な自衛と収益モデルの転換:本当に質の高い記事を提供しているなら、それを守るための戦略も必要です。実際、先進的なメディアはすでに取り組んでいますが、有料コンテンツへの移行や独自配信への投資は、もはや他人事ではありません。さらに技術的な自衛策として、例えばCloudflareが提供する『Pay Per Crawl』のような仕組みを使い、価値あるコンテンツが無制限にクロールされ、機械的に再利用されるのを防ぐといった戦略も視野に入れるべきでしょう。

ワンポイントアドバイス💡
🛡️ 守りのAEO: AIが「要約」できない、「引用」せざるを得ない、一次情報と深い洞察に満ちたコンテンツを作る。
⚔️ 攻めの脱依存: ニュースレターやコミュニティで、オーディエンスと直接繋がる「自分の庭」を育て、有料化や技術的な自衛策も検討する。
💎 本質で勝負: 「古参だから強い」は終わる。「本当に価値があるか」が問われる時代の到来を認識する。
歴史の転換点に、当事者として立つ
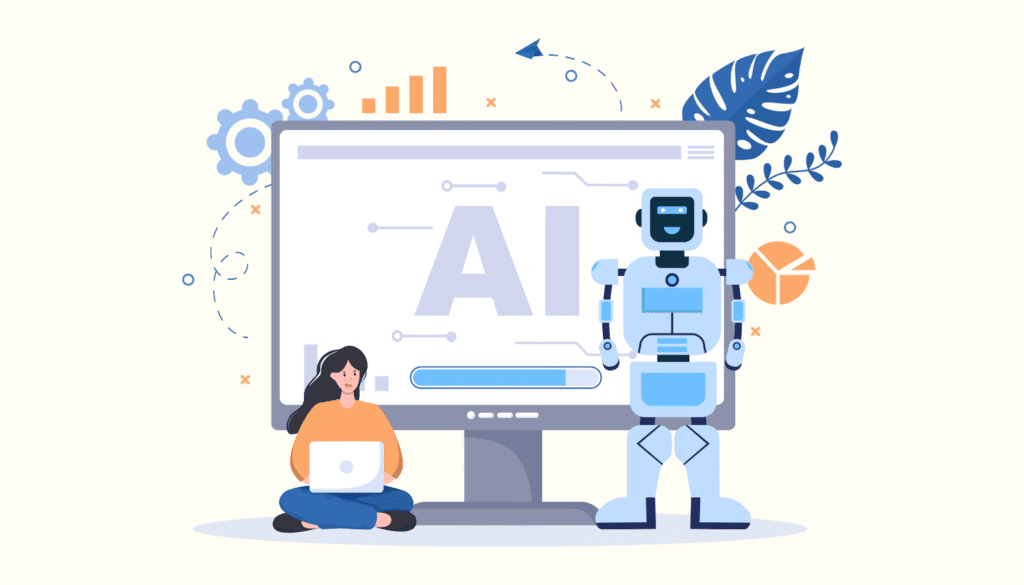
今回、欧州の出版社たちが起こした行動は、単なる一企業に対する申し立てではありません。AIという新しい技術と、私たち人間がどう向き合い、共に生きていくためのルール作りを始める、という歴史的な合図なのです。
GoogleのAI要約機能は、コンテンツ制作者の利益を奪ってしまう「共食い」のような側面を持ち、多くの人々に脅威を与えています。しかしその裏側では、コンテンツの「質」を見極め、本当に良いサイトへ人々を送り届ける、優れた「目利き役(キュレーター)」としての役割も果たしています。
このAIによる厳しい選別は、中身のない大量生産された記事や、ただ情報を右から左へ流すだけだったサイトの時代に終わりを告げるものです。そして、自分だけの独自性と信頼性を持つクリエイターこそが正当に評価される、新しい時代の幕開けを意味しています。
この変化には痛みが伴うかもしれません。しかし、質の高い専門知識を持つ私たちクリエイターにとっては、自分たちの価値が改めて認められる、またとないチャンスでもあります。私たちはこの変化の目撃者であり、当事者です。欧州での戦いの行方を見守りつつ、私たち自身も、自らの価値を守り、これからの時代に合わせた行動を、今日から始めていきませんか。
免責事項・注意事項
この記事は、2025年7月時点での公開情報や報道に基づき、デザイナーの視点から考察を加えたものです。AI技術、各社のサービス、法規制や訴訟の動向は非常に速く変化しています。最新の情報については、必ず公式サイトや信頼できる情報源をご確認ください。本記事の内容は、特定の行動を推奨するものではなく、いかなる損失についても責任を負いかねます。AIツールの利用やコンテンツ戦略の決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。
参考ソースリスト
この記事は、主に以下の情報源や公開されている情報を元に構成されています。
- Google AI Overviews 公式情報 – GoogleによるAI検索機能の公式な説明です。
- Googleクローラ(ユーザー エージェント)の概要 – Google-Extendedなど、技術的な仕様に関する公式ドキュメントです。
- Movement for an Open Web – 今回の申し立てを支援している団体の一つです。
- Cloudflare Pay Per Crawl – コンテンツのクロールを制御する技術的な選択肢の一つです。
- GoogleのAI要約機能に対するEU独占禁止法違反の申し立て – BestMediaInfo:独立系出版社連盟がGoogleのAI要約機能に対し、EUで独占禁止法違反の申し立てを行いました。
- EU、GoogleのAI要約機能に対する独占禁止法違反の申し立てを提出 – AInvest:GoogleのAI要約機能が出版社のトラフィックと収益に悪影響を与えているとして、EUで独占禁止法違反の申し立てが行われました。
- GoogleのAI要約機能に対するEUの独占禁止法違反申し立て – Reuters:独立系出版社グループがGoogleのAI要約機能に対し、コンテンツの無断使用とトラフィック・収益の損失を理由にEUに独占禁止法違反を申し立て。
- Google、AI要約機能に対するEUの独占禁止法違反申し立て – TechCrunch:独立系出版社連盟がGoogleのAI要約機能に対し、コンテンツの無断使用とトラフィック・収益の損失を理由にEUに独占禁止法違反を申し立て。
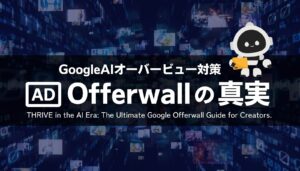
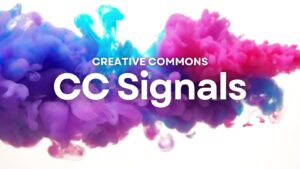
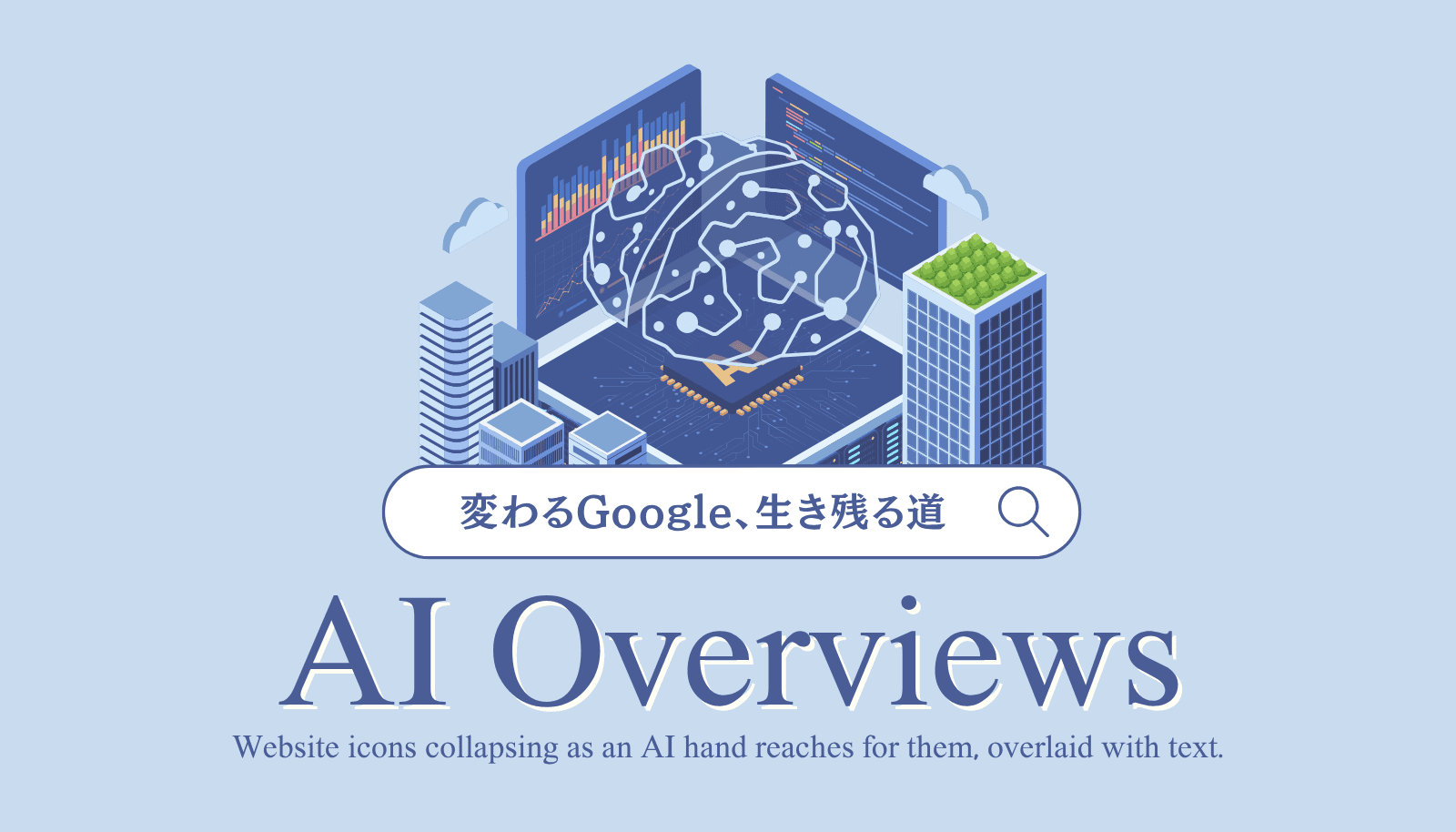
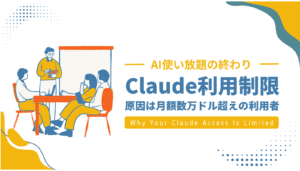

コメント