Creative Marketのサイトを訪れる楽しみの一つに、毎週更新される「Free Goods of the Week」がありますよね。私も火曜日になると、今週はどんな素敵な素材に出会えるだろうと、ワクワクしながらチェックしています。
そして、ハイクオリティなイラストやテンプレートを無料でダウンロード!…したは良いものの、「この”Personal License”って、具体的に何に使っていいんだろう?」と、ふと手が止まってしまった経験はありませんか?
「このイラスト、自分のブログの挿絵にしていいのかな?」
「SNSテンプレートって、収益化してない趣味のアカウントならOK?」
「せっかくもらったけど、結局使わずにフォルダに眠ってしまっている…」
この記事は、そんなあなたのための徹底ガイドです。パーソナルライセンスのルールを正しく、そして分かりやすく理解することは、トラブルを避けるだけでなく、手に入れた宝物のような素材たちを、安心して、最大限に活用することに繋がります。
ライセンスの「できること」「できないこと」を明確にし、あなたの個人的なクリエイティブ活動を、もっと自由に、もっと豊かにするための方法を一緒に見ていきましょう。
この記事で分かること📖
✅ なぜデザイナーはCreative Marketを選ぶのか? サービスの価値と背景
⚖️ パーソナルライセンスの明確な境界線:「やって良いこと」「ダメなこと」を徹底解説
💡 無料素材の具体的な活用法:イラスト、テンプレート、モックアップ等の実践的アイデア
🤔 クリエイターの悩み解決:ポートフォリオ、NPO協力、ブログなど、判断に迷うケースを解説
🚀 プロジェクトが成長したら?:商用ライセンスへの賢いステップアップ方法
なぜ今、Creative Marketがデザイナーに選ばれるのか?
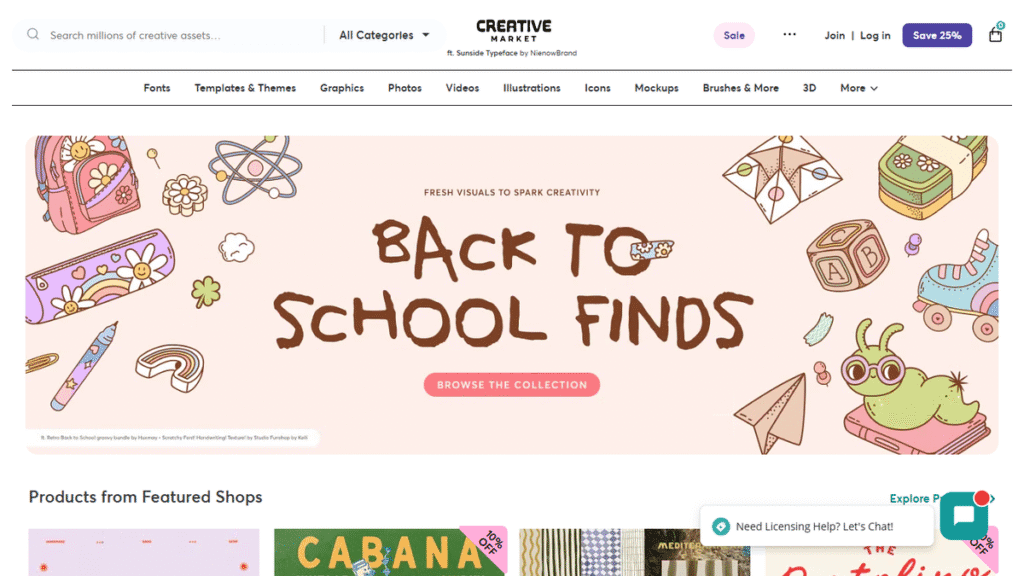
ライセンスの話に入る前に、少しだけ「なぜ私たちはCreative Marketというサービスに惹かれるのか」について、デザイナーの視点から掘り下げてみたいと思います。素材サイトは他にもたくさんある中で、Creative Marketが持つ独自の価値とは何でしょうか。
クリエイターによる、クリエイターのための市場
Creative Marketが他の多くの素材サイトと一線を画すのは、その成り立ちにあります。このサービスは、企業が制作した素材を販売するのではなく、世界中の個人のデザイナーやクリエイターが自分の店(ショップ)を開き、自作のアセットを直接販売する「マーケットプレイス(市場)」形式 を採用しています。まるで、クリエイターが集まる巨大なオンラインの蚤の市やアートマーケットのような場所です。
この仕組みを支える運営企業の背景も興味深いものです。Creative Marketは、2020年にデザイナー向けのポートフォリオサイトとして世界的に有名な Dribbble(ドリブル) に買収されました。Dribbbleは、デザイナーが自らの作品を公開し、フィードバックを得て、仕事に繋げるための巨大なコミュニティです。クリエイターの生態や価値観を深く理解している企業が運営しているからこそ、Creative Marketは単なる素材販売サイトに留まらず、トレンドの発信地となり、クリエイターのニーズに寄り添ったプラットフォームであり続けているのです。
私がCreative Marketを選ぶ理由
私自身、多くのプロジェクトでCreative Marketを活用していますが、その理由は主に3つあります。
- クオリティとトレンド感:
個人クリエイターが出品しているため、大手ストックフォトサービスにはない、ユニークで作家性の高いアセットが豊富です。世界の第一線で活躍するデザイナーが作るテンプレートやUIキットは、最新のデザイントレンドを色濃く反映しており、眺めているだけでも勉強になります。 - 圧倒的な「時短」効果:
質の高いテンプレートやグラフィックセットを使えば、デザインの土台を一瞬で作り上げることができます。例えば、UIキットを使えばアプリ画面の基本パーツをゼロから作る必要がなくなりますし、モックアップ素材を使えばプレゼン資料用のリアルな合成画像を数分で作成できます。この「時間を買う」という感覚は、AIを活用して単純作業を効率化し、より創造的な作業に集中したい、という私たちの考え方と非常にマッチします。 - インスピレーション:
単に素材を探すだけでなく、世界中のクリエイターがどんなものを作っているのかを見るだけでも、大きな刺激を受けます。自分では思いつかないような色の組み合わせ、新しいフォントの使い方、美しいレイアウト。Creative Marketは、私たちのデザインの引き出しを増やしてくれる、最高のインスピレーション源でもあるのです。
注目ポイント📌
🏢 運営はDribbble:クリエイターコミュニティの雄が運営する、信頼性の高いマーケットです。
🎨 作家性の高いアセット:個人のクリエイターが出店するため、ユニークで高品質な素材が豊富です。
⏳ 時間を買うという価値:テンプレートやキットの活用は、AI時代における賢い時間創出術です。
パーソナルライセンスの核心:3つの絶対ルール

さて、本題のライセンスの話に戻りましょう。パーソナルライセンスを使いこなすための第一歩は、その根幹を成す最も大切なルールを理解することです。Creative Marketの規約では、「個人利用(Personal Use)」とは、「商用利用の基準のいずれにも該当しない利用」と定義されています。
これはつまり、「これから挙げる3つの条件をすべてクリアしているものだけが、個人利用と認められます」ということです。この3つは、ライセンスを守る上での土台となる部分。一つでも外れると、それは「商用利用」と見なされてしまうので、しっかりと頭に入れておきましょう。
- ルール1:金銭のやり取りが一切発生しないこと
これは最もシンプルで分かりやすいルールです。あなたが作るプロジェクトに関連して、どんな形であれ、お金を受け取ってはいけません。例えば、友人から「デザインはタダでいいから、印刷代だけ受け取って」と言われたとしても、それは金銭の授受にあたり、パーソナルライセンスの範囲を超えてしまいます。 - ルール2:いかなる事業体の宣伝にもならないこと
これも重要なポイントです。あなたの制作物が、営利・非営利を問わず、どんな会社や組織の宣伝・広報活動にも使われてはならない、ということです。多くの人が見落としがちなのが「非営利団体(NPO)」も、この「事業体」に含まれるという点。後ほど詳しく解説しますが、ここが大きな落とし穴になります。 - ルール3:直接的または間接的な金銭的利益を生じないこと
これが最も解釈が広く、慎重な判断が求められるルールです。その制作物を使うことで、直接的にお金儲けを意図していなくても、結果的にあなたの利益に繋がるような使い方はNGとなります。例えば、商品レビューでアフィリエイトリンクを貼っているブログで、記事の挿絵としてアセットを使う、といったケースがこれにあたります。
この3つのルールは、「AND条件」です。つまり、「1も2も3も、すべてYES」である必要があります。一つでも「NO」があれば、その時点でパーソナルライセンスの範囲外。その場合は、コマーシャルライセンスなど、別のライセンスが必要になる、と覚えておいてください。
注目ポイント📌
📜 3つの絶対ルールは、金銭授受なし、事業宣伝なし、利益発生なし、です。
⚖️ 一つでも破れば商用利用と見なされ、自動的にライセンス違反になるので要注意です。
🤔 「間接的な利益」の解釈が鍵となり、自分の活動がどう見られるか、客観的な視点を持つことが大切です。
クリエイターが直面するライセンスの「壁」
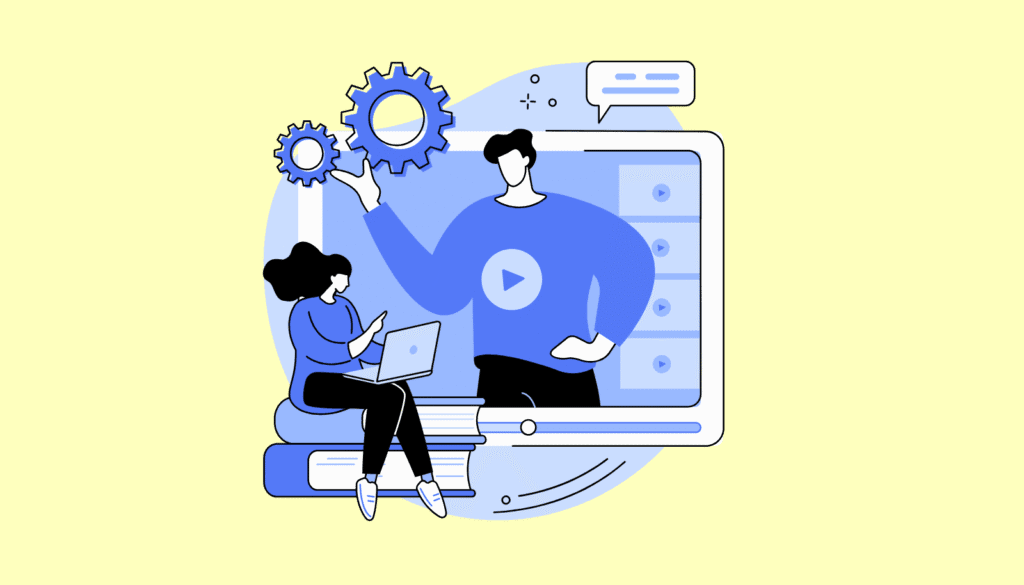
3つの基本ルールは理解できた。でも、実際のクリエイティブシーンでは「これってどっちなんだろう?」と悩むような、判断が難しい場面が数多く存在します。ここでは、特に私たちクリエイターが直面しがちな、判断に迷うシナリオを具体的に見ていきましょう。ここを理解することが、トラブルを未然に防ぐ鍵になります。
「ポートフォリオ問題」を乗り越える思考法
これは多くのデザイナーにとって、本当に頭の痛い問題です。
ポートフォリオとは、デザイナーやクリエイターが、自分のスキルや実績をアピールするために作品をまとめた「作品集」のこと。これからの仕事に繋げるために、不可欠なツールです。
しかし、パーソナルライセンスのアセットを使って制作した作品を、そこに載せてもいいのでしょうか?
結論から言うと、そのポートフォリオを仕事獲得のために使うのであれば、厳密にはNGとなる可能性が非常に高いです。
なぜなら、仕事獲得を目的としたポートフォリオは、ライセンス規約が禁じている「金銭的利益を得ることを意図」し、「自身のスキルという事業サービスを宣伝する」行為そのものに他ならないからです。この根本的な矛盾を、私たちは認識しておく必要があります。
「じゃあ、スキルアップのために作った習作は、誰にも見せられないの?」
そんなことはありません。希望はあります。鍵となるのは、その作品の「見せ方」と「位置づけ」です。
- アプローチ1:「クライアントワーク」として見せない
その作品が、実際のクライアントから依頼を受けて制作したものではないことを明確にしましょう。 - アプローチ2:「コンセプトデザイン」や「習作」と明記する
「これはパーソナルライセンスのアセットを使用して制作した、架空のプロジェクトのコンセプトデザインです」といった注釈を添えることで、直接的な営業ツールとしての色合いを薄め、あくまで自身のスキル探求のためのアウトプットであることを示すことができます。
もし、面接などでその作品について質問されたら、正直にその旨を説明しましょう。そして、万が一「そのデザインを実際に使いたい」という話になった場合は、速やかにコマーシャルライセンスを購入する意思があることを伝えるのが、誠実で賢明な対応です。
「非営利団体への協力」の落とし穴
「非営利」と聞くと、私たちはつい「非商用」と同じだと考えてしまいがちです。純粋な善意で、地域のNPOやボランティア団体のポスターを無償でデザインする。これは、どう考えても個人利用の範囲内じゃないか、と思いますよね。
しかし、Creative Marketのライセンス規約では、非営利団体も「事業体」として扱われます。
これは、Creative Marketが定義する「事業」が、利益を追求しているかどうかではなく、その組織の構造や活動内容に基づいているからです。非営利団体も、寄付を集めたり、活動を広めたりするために、広報や宣伝活動を行います。
- パーソナルライセンスのアセットを使ったチラシで、チャリティイベントへの参加を呼びかける。
- これは「事業の宣伝」にあたります。
- そのチラシを見てイベントに参加した人が寄付をする。
- あなたの制作物が「間接的な金銭的利益」を生んだ、と見なされます。
したがって、たとえあなたが1円も受け取らない完全なボランティアであっても、非営利団体のための制作物にパーソナルライセンスのアセットを使用することはできません。このケースでは、コマーシャルライセンスの購入が必須です。私たちの一般的な感覚と、ライセンス上の厳密な定義との間には、これだけの隔たりがあるのです。
「個人ブログ」がビジネスに変わる瞬間
パーソナルライセンスでは、「非商用活動を行う個人のソーシャルメディアアカウント1つ」での利用が許可されています。趣味のブログやSNSで、購入した素敵なグラフィックを使って世界観を表現するのは、とても楽しいですよね。
しかし、その活動がいつ「商用」に変わるのか、その境界線は非常に曖昧で、そしてシビアです。
転換点となるのは、「収益化」です。
あなたのブログやSNSに、たった一つでもアフィリエイトリンクや広告(Google AdSenseなど)、あるいはスポンサー付きの投稿が掲載された瞬間、その場所は「間接的な金銭的利益を生む」プラットフォームへと変貌します。
この変化は、ライセンス契約に致命的な影響を及まします。収益化された時点で、そのブログはライセンス上「商用」と判断され、ヘッダーや記事の挿絵に使っていたパーソナルライセンスのアセットは、すべて規約違反の状態になってしまいます。
合法的にアセットを使い続けるためには、コマーシャルライセンスを新たに購入し直す以外に方法はありません。個人の活動が少しずつ成長していく過程で、本当によくあるケースです。自分のサイトの状況は、常に意識しておく必要があります。
注意事項📌
💼 ポートフォリオ掲載は要注意。営業ツールと見なされるリスクを理解し、「習作」として見せる工夫をしましょう。
🤝 非営利でも商用扱いになります。善意のボランティアでも、団体のための制作はコマーシャルライセンスが必要です。
💰 収益化が境界線です。広告やアフィリエイトを1つでも貼ったら、あなたのサイトは「商用」と見なされます。
【商用利用の重要ルール】デザイナーが知るべき3つのポイント
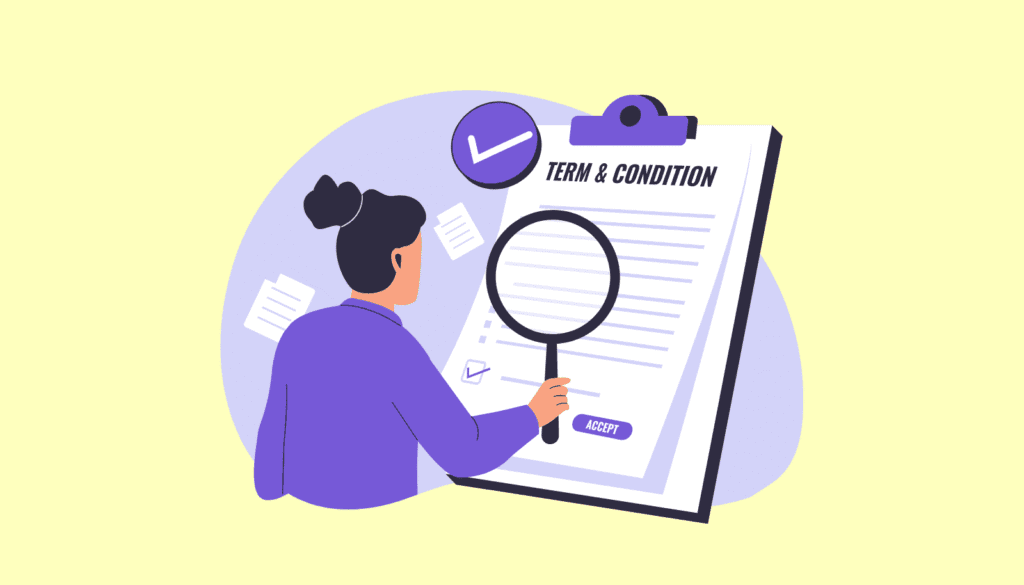
パーソナルライセンスの範囲を超えて、いよいよ商用ライセンス(Commercial / Extended Commercial)を活用する段階に進む前に、デザイナーが必ず知っておくべき重要なルールがいくつかあります。ここを理解することが、プロとして活動する上での信頼に繋がります。
ポイント1:「大幅な変更」を加える義務
これは、特に商用ライセンス(Commercial License)における最も重要なルールの一つです。ライセンス規約には、商用目的で作成される最終製品(End Product)は、以下の条件を満たす必要があると明記されています。
- 元の素材から大幅に異なっていること
- 制作に時間、労力、スキルを要すること
- 製品の主な価値が、元の素材そのものから来ているものではないこと
これはつまり、「素材をダウンロードして、そのままTシャツにプリントして販売する」といった使い方は禁止されているということです。Creative Marketが求めているのは、購入した素材を「部品」として使い、そこにデザイナー自身の創造性やアイデアという「付加価値」を加えて、まったく新しいデザインを生み出すことです。
ポイント2:ロゴへの利用と商標登録のルール
イラストや写真をロゴの一部として使うことは、商用ライセンスまたは拡張商用ライセンスで許可されています。しかし、ここにも厳密なルールがあります。
- 素材に変更を加えること:元の素材をそのままロゴにすることはできません。
- ロゴの主要な要素にしないこと:ロゴ全体のデザインの中で、購入した素材が「主役」になってはいけません。
- 商標登録時の権利不要求:もしそのロゴを商標として登録する場合、使用した素材部分の権利は主張できません。
ロゴは企業の顔です。他者も利用可能な素材を元に作る際は、こうしたルールを遵守し、独自性を確保する必要があります。
ポイント3:広告における地理的な制限
商用ライセンスは、広告での利用も許可していますが、物理的な広告(看板や印刷物など)には地理的な制限が設けられています。
- 商用ライセンス (Commercial): 物理広告の表示・配布は「ローカル市場」(単一国内の半径200マイル/約320km圏内)に限定されます。
- 拡張商用ライセンス (Extended Commercial): この制限がなくなり、国内全域(ナショナル)や全世界(グローバル)での物理広告展開が可能になります。
一方で、デジタル広告(Web広告など)については、どちらのライセンスでもインプレッション(表示回数)の制限はありません。
ワンポイントアドバイス📌
✍️ 商用利用は「付加価値」が必須。素材をそのまま使うのではなく、自分のスキルで新しい価値を生み出しましょう。
🏢 ロゴ利用は慎重に。商標登録も視野に入れるなら、ルールを深く理解するか、専門家への相談が賢明です。
🌍 広告展開の規模を意識して、適切な商用ライセンスを選ぶことが重要です。
絶対NG!すべてのライセンスに共通する禁止事項
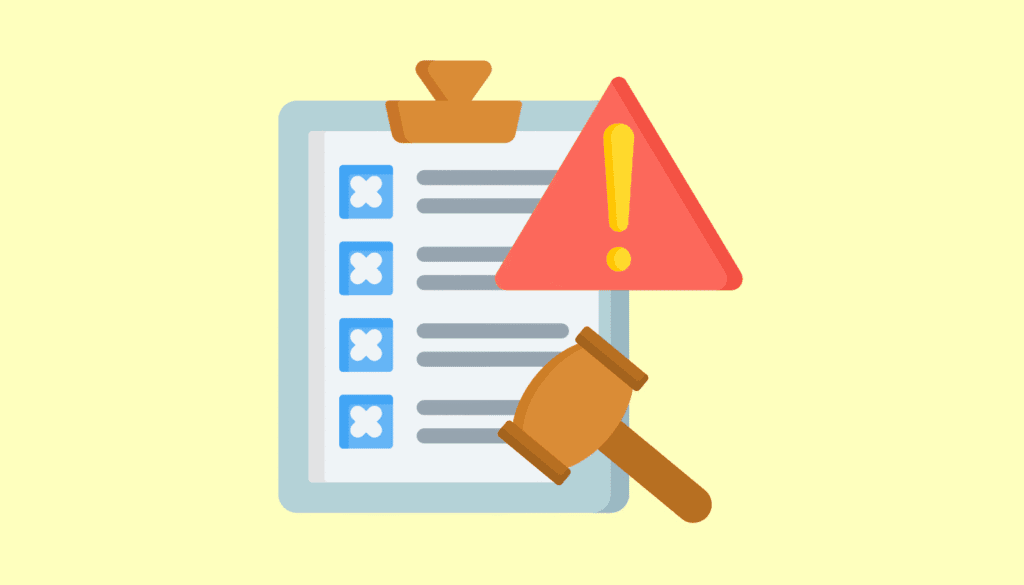
ここでは、パーソナルか商用かを問わず、すべてのライセンスで共通して禁止されている、特に重要な行為を確認します。
- 再販・サブライセンスの禁止:
購入したアセットを、素材としてそのまま、あるいは少し変更を加えただけで、第三者に販売・再配布することは固く禁じられています。例えば、購入したテクスチャパックの一部を、自分の素材集として販売するような行為はNGです。 - オンデマンドサービスでの利用禁止:
プリントオンデマンド(POD)や「メイド・トゥ・オーダー」のような、エンドユーザーがデザインをカスタマイズできるサービスでアセットを使用することは、ライセンスの種類を問わず禁止されています。これは、アセットの管理が困難になり、意図しない再配布に繋がるためです。 - 不適切なコンテンツでの使用禁止:
ポルノ、詐欺的、中傷的、非合法、嫌がらせ、攻撃的といった、公序良俗に反するコンテンツにアセットを使用することは、当然ながら禁止されています。
無料素材をフル活用!パーソナルライセンスで広がる創造のアイデア
さて、ここからが本番です。毎週手に入る無料素材の多くは、このパーソナルライセンスです。ルールをしっかり理解すれば、これらの宝物を安心して、そして存分に楽しむことができます。せっかくダウンロードした素材、眠らせておくのはもったいない!
ここでは、私自身が毎週の無料素材をどのようにストックし、次のクリエイティブに繋げているか、具体的な活用法を素材の種類別にご紹介します。
イラスト素材:プロの時短術としての「お試し利用」
無料配布で最もよく見かけるイラスト素材。私はこれらを「水彩風」「線画」「アイコン」といったように、自分なりにジャンル分けしてストックしています。このストックが、新しいデザインを考える時の「アイデアの引き出し」として大活躍するんです。
具体的な使い方としては、まずラフデザインの段階で、合いそうなイラストを仮で配置してみます。Creative Marketの素材は高品質でユニークなものが多いため、従来の透かし入りカンプ画像(ダミー画像)や、ありきたりな図形で代用するよりも、完成形のイメージがリアルに湧いてきます。これが制作のモチベーションを上げてくれますし、手戻りが減ることで結果的に時短にも繋がるんです。
そして、「この方向性でいけそうだ!」と自分の納得が得られたり、クライアントにラフを確認してもらってOKが出たら、その時点ですぐに商用ライセンスを購入します。このやり方なら、無駄な投資をすることなく、最高の素材で高品質な完成品を目指せます。
(※ただし、クライアントにラフを見せる際は、あくまで仮のものであり、本採用の際には正規ライセンスを取得する旨を一言伝えておくと、より丁寧で安心です。)
テンプレート・モックアップ:その価値を「体感」するための試用
正直なところ、普段あまりテンプレートやモックアップを使わない、という方もいるかもしれません。私も以前はそうでした。だからこそ、無料配布は「食わず嫌い」を克服する絶好の機会なんです。
実際に自分の作品や手持ちの画像をテンプレートに当てはめてみると、その圧倒的なクオリティと時短効果に驚かされます。「これを自力で作ったら何時間かかるだろう…」と考えてみると、その価値がよく分かります。
こうして一度でも価値を体感しておくと、今後の実務で「この案件なら、あのタイプのモックアップが有効だな」「急ぎのSNS投稿は、テンプレートを活用しよう」というように、制作の選択肢が格段に広がります。 無料素材で「慣れておく」ことは、未来の自分の仕事を助ける、賢い自己投資と言えますね。
プリセットやブラシ:「武器」を増やし表現力を高める
LightroomのプリセットやProcreate用のブラシなどは、私たちの表現力を直接高めてくれるアイテムです。
- 個人的な写真をとことん追求する: 家族旅行や日常のスナップ写真を、プリセットを使ってプロのような雰囲気に仕上げる。様々なプリセットを試すことで、自分の写真表現の幅が広がります。
- お絵描きをとことん楽しむ: ユニークなブラシを手に入れれば、新しいタッチやテクスチャのイラストに挑戦できます。デジタルイラストの練習や、趣味で描く作品のクオリティアップに直結します。
注目ポイント📌
🎨 アイデアは無限大:無料素材は、プロの制作フローの「お試し」から、スキルアップのための「体感ツール」まで、使い道がたくさんあります。
📥 眠らせず、まず使ってみる:せっかく手に入れた素材です。まずは何か一つ、個人的なプロジェクトで試してみましょう。
👨💻 スキルアップのきっかけに:モックアップやブラシは、新しいデザインや表現に挑戦する絶好の機会になります。
一歩踏み込んだライセンス知識:フォントとクライアントワーク
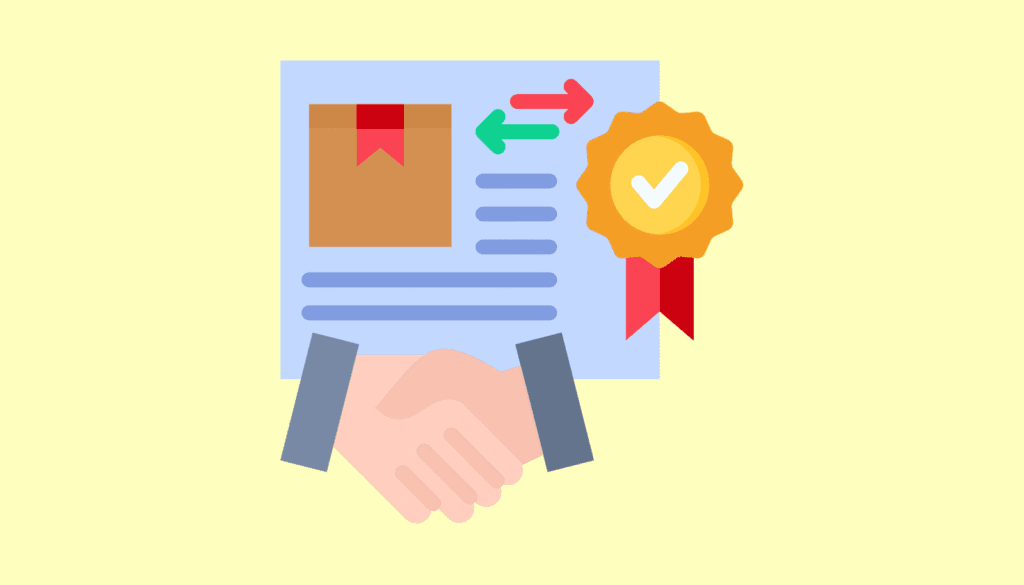
ちなみに、無料配布されるフォントは多くの場合、パーソナルライセンスではなく、商用利用も可能な「デスクトップライセンス」です。しかし、このデスクトップライセンスにも、デザイナーが知っておくべき重要なルールがいくつかあります。ここで合わせて確認しておきましょう。
なぜフォントライセンスは別物なのか?
Creative Marketのアセットは、大きく分けて2種類あります。
- 一般ライセンス (General Licenses): グラフィック、テンプレート、写真など。
- フォントライセンス (Font Licenses): フォント専用のライセンス。
なぜフォントだけが特別扱いなのでしょうか?それは、フォントが単なる「画像」ではなく、PCやウェブサイト、アプリなどに「インストール」「埋め込み」して使う「ソフトウェア」としての側面を持つからです。そのため、使用する場面(デスクトップ、ウェブ、アプリなど)に応じて、より細かいルールが定められているのです。
デスクトップライセンスで知っておくべき重要ルール
商用利用可能なデスクトップライセンスは、最も一般的なフォントライセンスですが、デザイナーが知っておくべき重要なルールがいくつかあります。
- ロゴへの使用と商標登録:
フォントを使ってロゴをデザインすることは可能です。しかし、そのロゴを商標登録する際には注意が必要です。フォント自体がロゴの主要な要素でないようにデザインを調整し、登録時にはフォント部分の権利を主張しない(権利不要求/ディスクレイマー)必要があります。 - クライアントワークでの使用:
クライアントのために制作を行う場合、完成した制作物(例:ロゴの画像データや印刷されたパンフレット)をクライアントに渡すことは問題ありません。これはサブライセンスの例外として認められています。 - 外部制作者との共有:
もしフリーランサーや外部の代理店に制作を委託する場合、その制作者にフォントデータを一時的に共有することも許可されています。ただし、その制作者もライセンスユーザーとしてカウントする必要があります。例えば、自分とフリーランサーの2名がそのフォントを使うなら、2ユーザー分のライセンスを購入する必要がある、ということです。 - Webfontライセンスとの混同:
Webfontライセンスで購入したフォントファイル(.woffなど)を、PCにインストールしてデザイン作業に使うことは禁止されています。逆もまた然りです。デスクトップでのデザインとウェブサイトでの表示、両方で同じフォントを使いたい場合は、デスクトップライセンスとWebfontライセンスの両方を購入する必要があります。
商用への道:プロジェクトが飛躍する時
もし、あなたの非商用プロジェクトが人気を博し、「これをビジネスにしたい!」と考え始めたらどうすればよいでしょうか。
多くの人が「パーソナルライセンスからコマーシャルライセンスへ、差額を払ってアップグレードできるのでは?」と考えますが、現在のCreative Marketの仕組みでは、そのような正式な「アップグレード」の仕組みは存在しません。
ライセンスの範囲を超える利用が必要になった場合に取るべき、唯一の正しい方法は、
「そのアセットの、別のライセンス(コマーシャルライセンスなど)を新たに購入する」
ことです。
これは、「アップグレード」ではなく「新規購入」です。この仕組みは、安価なパーソナルライセンスで始めて、後から都合よく商用利用に切り替える、ということを防ぎ、クリエイター(ショップオーナー)の正当な利益を守るためのものです。ですから、「もしプロジェクトが商用になったら、使っているアセットのコマーシャルライセンスを買い直す」と覚えておいてください。
注目ポイント📌
🖋️ フォントはソフトウェアと心得て、使用場面に合ったライセンスを選びましょう。
🤝 クライアントワークはルールを守ればOK。外部との連携ではユーザー数に注意が必要です。
🚀 アップグレードは存在しません。商用化の際は、コマーシャルライセンスを「新規購入」すると覚えましょう。
まとめ
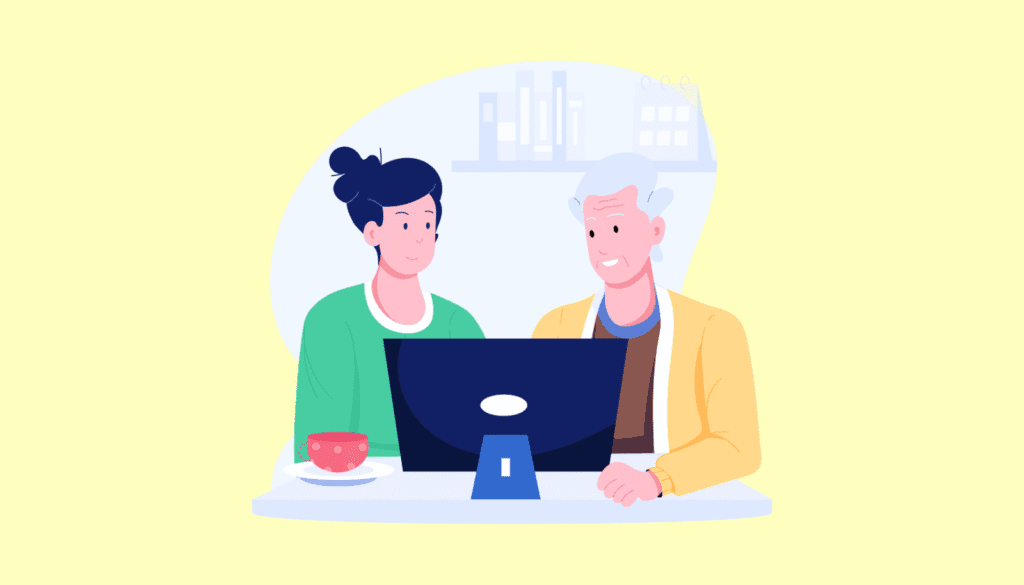
Creative Marketのパーソナルライセンスは、規約上「商用利用不可」と定められています。
このライセンスのルールを正確に理解することで、毎週無料で配布されるイラスト、テンプレート、ブラシといった素材を、規約違反の懸念なく個人のプロジェクトに活用できます。
AIによる作業自動化が進む現代において、クリエイターが創造的な活動に使える時間は限られています。ライセンスの解釈に迷う時間は、制作の非効率に直結します。
この記事の目的は、Creative Marketのパーソナルライセンスに関する明確な情報を提供して、読者が迷うことなく、効率的に制作活動に取り組めるように支援することです。
当ブログでは、この記事で解説したライセンスで利用できる、毎週の無料アセット紹介も行っていますので、そちらもぜひ創作活動にお役立てください。
【免責事項】本記事の情報の取り扱いについて(お願い)
本記事で扱うライセンスに関するテーマは、サービスの規約変更などによって、将来的に解釈が変わる可能性があります。また、法的な解釈がまだ定まっていない部分を含む場合があります。この記事は、デザイナーである筆者がクリエイターの視点から情報を整理し、皆様と共に考えるための情報提供を目的として執筆したものです。そのため、掲載された情報が最新でない可能性や、あくまで解釈の一つに過ぎない場合があることをご理解ください。法的な助言として、またその内容の完全な正確性を保証するものではありません。本記事の内容を参照したことによって生じたいかなる損害についても、当ブログでは責任を負いかねますことを、あらかじめご了承ください。最新の情報や正確な法的判断が必要な場合は、必ず一次情報源(Creative Market公式サイトなど)をご確認の上、必要に応じて弁護士などの専門家にご相談いただきますようお願い申し上げます。
参考ソース
- Personal License FAQ – Creative Market
- General Licenses – Creative Market
- Licenses & Non-Profit Organizations – Creative Market
- Extended Commercial License FAQ – Creative Market
- Which license should I choose: Commercial or Extended Commercial? – Creative Market

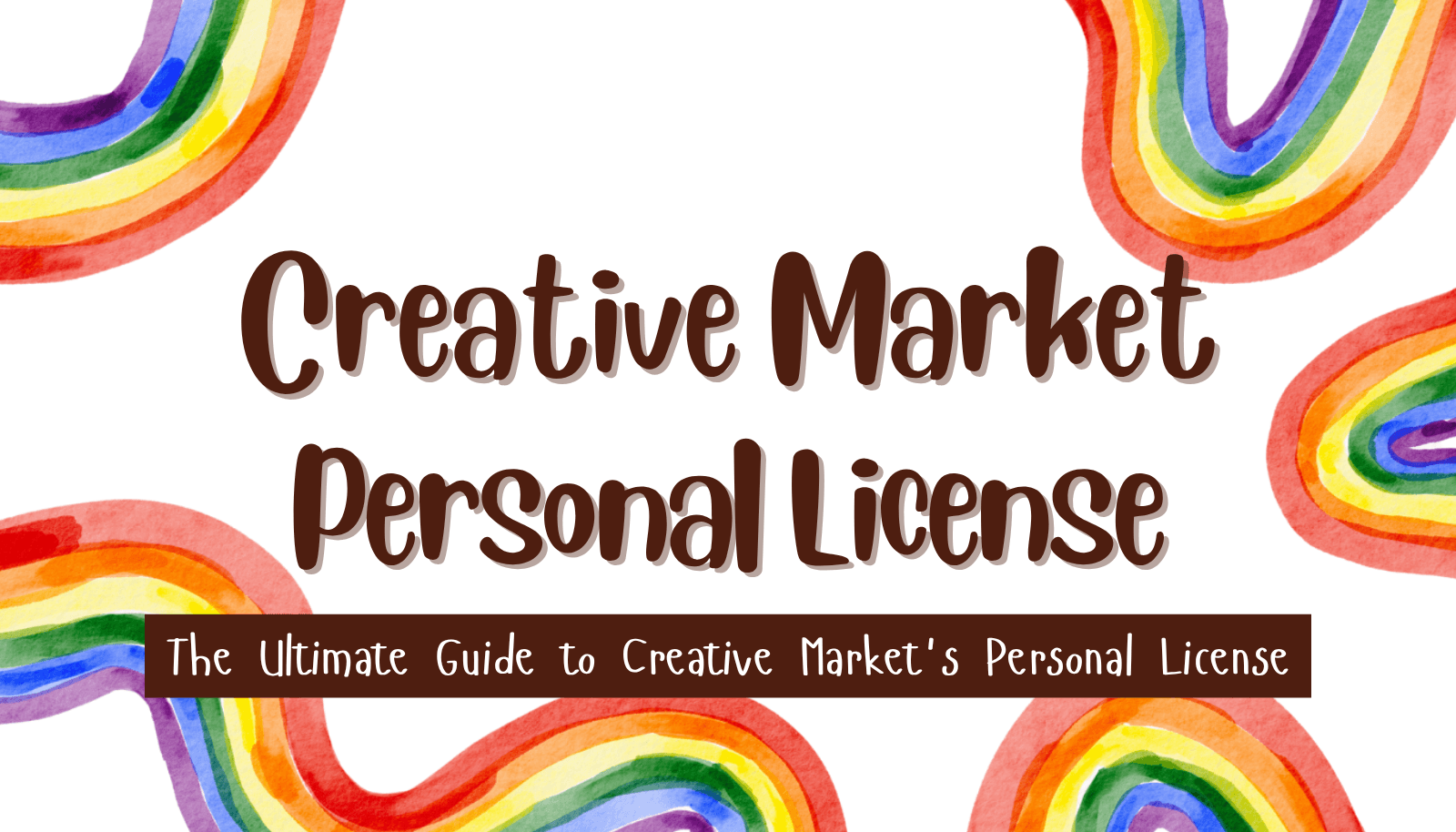


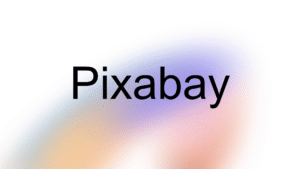
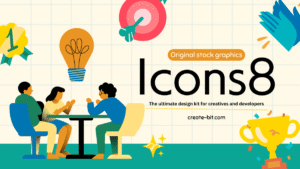

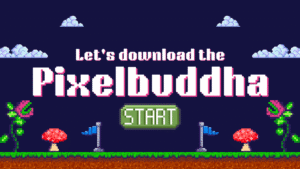
コメント