CreateBitは、「AIを活用してクリエイティブな時間を確保する」というコンセプトのもと、AI時代のクリエイターの働き方や思考法について情報を発信しています。
このコンセプトを実現する上で、私自身がどのようにAIと向き合い、記事を制作しているのか。そのプロセスと基本方針を透明性をもってお伝えすることは、読者の皆様との信頼関係を築く上で不可欠だと考えています。
Googleは、検索のガイダンスの中で「コンテンツがどのように作成されたかについての情報」を読者に提供することを推奨しています。このポリシーページは、その指針を実践し、私のコンテンツ制作におけるAIの活用哲学と具体的なルールを、誠実にお伝えするものです。
私が考えるAIとの理想的な関係
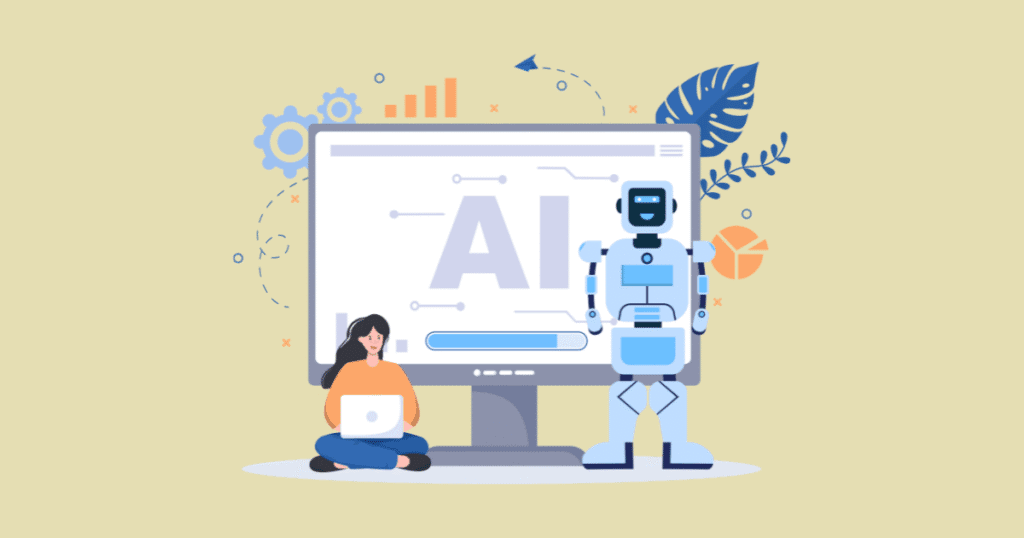
CreateBitの根底にあるのは、「AIはクリエイターの仕事を奪うものではなく、クリエイティブな活動を加速させるための強力なパートナーである」という考え方です。
CreateBitのメインコンセプトは、「制作活動をAIに丸投げするのではなく、AIをあくまでパートナーとして活用し、人間がより創造的な時間を確保するための思考法やヒントを発信する」ことです。これは、記事制作をAIに丸投げする姿勢とは明確に一線を画します。
私がAIに期待するのは、アイデア出しの壁打ち、膨大な情報のリサーチ補助、複雑な情報の整理、そして文章の校正といった、クリエイティブな思考を深める前の準備段階や、品質を高めるための補助的な作業です。これらの単純作業や事務的なプロセスをAIに任せることで、私人間は、人間ならではのクリエイティブな活動、つまり本当に価値のある部分により多くの時間を注ぐことができるようになります。
具体的なAI活用プロセスと人間の役割
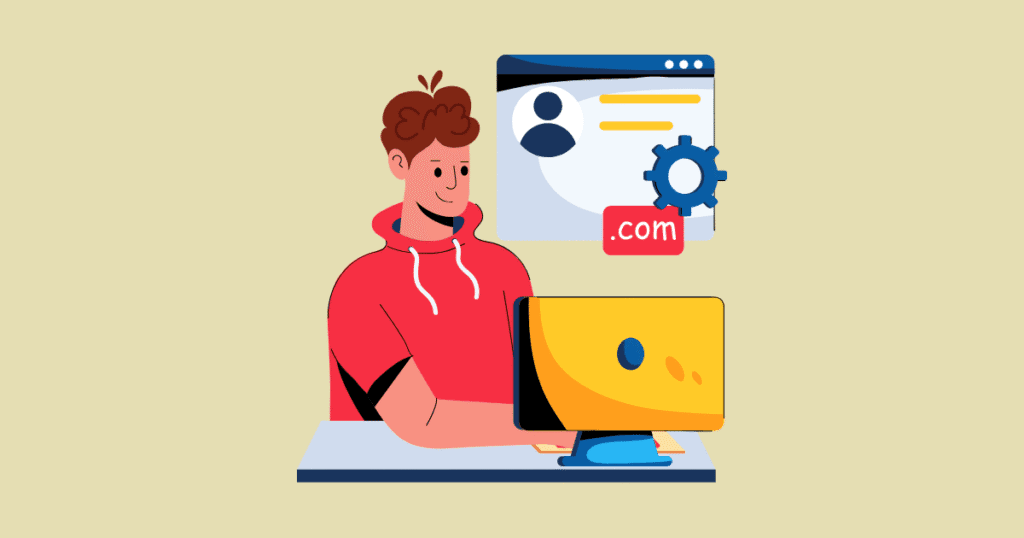
CreateBitの記事は、AIの能力と人間の創造性を組み合わせることで制作されています。AIが生成したテキストをそのまま公開することは決してありません。すべての記事は、以下のプロセスを経て、運営者自身が責任を持って最終的な品質を担保しています。
AIが担う領域:効率化とアイデアの拡張
記事制作のプロセスにおいて、AIは主に以下の役割を担います。
- リサーチ補助:テーマに関する広範な情報収集や、信頼できる情報源のリストアップをAIに依頼し、リサーチ時間を大幅に短縮します。
- 構成案の作成:読者の検索意図を分析し、論理的で分かりやすい記事の骨子や見出し構成のたたき台を作成させます。
- 複雑な情報の整理と要約:専門的な内容や難解な文章を、読者にとって理解しやすい言葉で要約・整理させます。
- 文章の校正と表現の提案:誤字脱字のチェックや、より伝わりやすい表現の提案を受け、文章の品質を向上させます。
人間が担う領域:品質の担保とE-E-A-Tの注入
AIによる下準備を経て、ここからが人間であるクリエイターとしての本領発揮の場となります。Googleが品質評価で重視する「E-E-A-T」を担保するのは、人間の重要な役割です。
- 事実確認:AIが提示した情報に誤りがないか、一次情報や信頼できる情報源を元に徹底的に確認します。これは、コンテンツの信頼性を確保するための最も重要なプロセスです。
- 経験と専門性:私自身のデザイナーやブロガーとしての実体験に基づいた考察や具体的な事例、専門知識をふんだんに盛り込みます。AIには生成できない、一次情報としての「経験」こそが、記事に深みと独自性を与えます。
- 編集・加筆・修正:AIが作成した構成案や文章は、あくまで「下書き」です。読者にとって最も価値のある情報は何かを常に考え、全体の流れを再構築し、不要な部分を削り、人間ならではの洞察や分析を大幅に加筆します。
- 最終的な品質責任:記事のタイトルから本文、すべてのコンテンツに最終的な責任を持ちます。読者の皆様に誤解や不利益を与えることのないよう、細心の注意を払って公開しています。
Googleの指針と私のコンテンツ制作ポリシー

当サイトは、読者の皆様に有益な情報を提供すると同時に、検索エンジンからも正当に評価される誠実なサイト運営を目指しています。そのため、Googleが定める各種ガイドラインを深く理解し、それを遵守することを基本方針としています。
ユーザー第一のコンテンツ制作
私は、Googleが掲げる「検索の基本事項」の中核である「有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツを作成する」というベストプラクティスに強く共感し、これを私のコンテンツ制作における第一の原則としています。AIを活用する目的も、この原則をより高いレベルで実現するためです。AIによる効率化は、読者の皆様にとって本当に価値のある情報は何かを考え、それを形にするための時間を確保するための手段に他なりません。
スパムに関するポリシーの遵守
Googleは、検索順位の操作を主な目的とした、価値の低いコンテンツの大量生成を「大量生成されたコンテンツの不正使用(Scaled Content Abuse)」として厳しく禁じています。
Google ウェブ検索のスパムに関するポリシーより引用:
「大量生成されたコンテンツの不正使用とは、ユーザーをサポートすることではなく、検索ランキングの操作を主な目的として大量のページを生成することを指します。」
CreateBitにおけるAI活用は、このようなスパム行為とは明確に一線を画します。私の目的は、AIを使って記事を量産することではなく、一本一本の記事に人間ならではの価値を付加し、品質を高めることです。
E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)の追求
Googleの「検索品質評価者向けガイドライン」では、コンテンツの品質を評価する重要な指標として「E-E-A-T」が挙げられています。特に信頼性(Trust)が最も重要な中心的概念とされています。
- Experience(経験):コンテンツ制作者が持つ、トピックに関する実体験。
- Expertise(専門性):テーマに関する専門的な知識やスキル。
- Authoritativeness(権威性):その分野における第一人者としての評価。
- Trust(信頼性):ページの正確性、誠実さ、安全性。
私は、AIの活用がこのE-E-A-T、特に「信頼性(Trust)」を損なうことがないよう、細心の注意を払っています。AIは専門性(Expertise)のある情報を整理することはできますが、実体験に基づく経験(Experience)や、最終的な情報の信頼性(Trust)を担保することはできません。それらは、コンテンツに責任を持つ人間の役割です。
YMYL(Your Money or Your Life)トピックへの配慮
YMYLとは、人々の健康、経済的安定、安全、または社会の幸福や福祉に大きな影響を与える可能性のあるトピックを指します。 Googleは、これらのトピックを扱うページに対して、特に高い品質基準を求めています。
CreateBitでクリエイターの働き方や収入、メンタルヘルスなど、YMYLに該当しうるテーマを扱う際は、情報の正確性と信頼性を最大限に重視します。個人的な経験を共有する場合は、それが専門的なアドバイスではないことを明確にし、必要に応じて専門家や公的機関の情報源を引用・紹介するなど、慎重なコンテンツ作りを心がけます。
透明性の確保
繰り返しになりますが、Googleは「コンテンツがどのように作成されたか」を読者に伝えることを推奨しています。このポリシーページを公開すること自体が、その指針を実践する私の意思表示です。私は、これからも制作プロセスの透明性を大切にし、読者の皆様との誠実なコミュニケーションを続けていきます。
まとめ
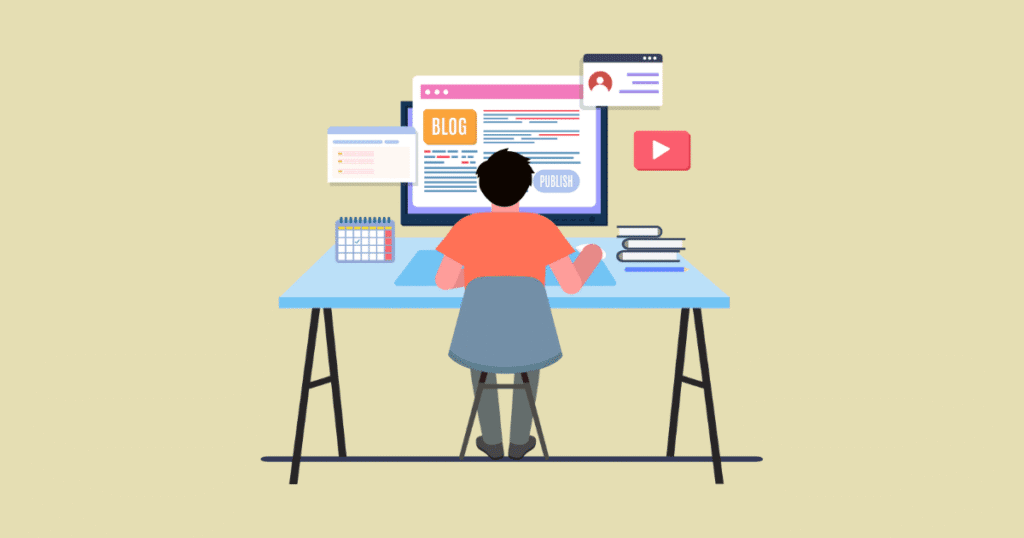
CreateBitでは、AIをクリエイティブ的な活動を支える強力なパートナーと位置づけ、記事制作の効率化と品質向上のために積極的に活用しています。
しかし、AIはあくまで補助的なツールです。すべての記事の最終的な品質と信頼性は、運営者である私自身が、Googleのガイドラインを遵守し、「ユーザー第一」の精神とE-E-A-Tを重視しながら、責任を持って担保しています。
このポリシーは、私の活動の透明性を確保し、読者の皆様との信頼関係をより深めるためのものです。今後も状況の変化に応じて内容を更新し、常に誠実なサイト運営を心がけてまいります。
この基本方針に関するご質問やご意見がございましたら、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。
📚 参考ソース